婦人科として地域のお産を守る

- 岩田レディースクリニック
院長 岩田 守弘
URL:http://www.iwata-ladies.com/
- 先生の出産に対する考え方を教えてください。
- とにかく無事安全にお産できるように、それを一番に考えています。どんな出産がしたいとか、急変した時の対応力とかって、妊婦さんがかかっている病院にもよるから、それはちゃんと妊婦さんには初めに理解しておいてもらいたいですね。自分の所はもうお産を取り扱っていない産婦人科クリニックだけど、妊婦健診をしている以上、お産に至るまで出来る範囲で対応、バックアップをして、情報提供もしていかないといけないと思ってます。だから、学会や研究会とかには積極的に出るようにして情報を収集するようにしています。それが、少しでも安全で適切な医療の提供につながると思っているので。
それから、以前に勤めていた病院が対応しているという経緯もあるのですが、妊婦さんに対して少しでも責任を持って健診していきたいという意味で、条件が合う場合はセミオープンシステムを取り入れています。≪セミオープンシステムとは??≫
妊娠32から36週頃までは妊婦健診は診療所で受診し、それ以降は病院で受診し、分娩の際も病院に入院し、病院の医師が分娩を扱うシステムのことです。
- 地域の分娩施設との連携が大切になってくると思うのですが。
 個人的には、いずれはお産のセンター集約化が必要になってくるかなと思ってます。
個人的には、いずれはお産のセンター集約化が必要になってくるかなと思ってます。
今現在一生懸命お産をやっておられる開業医の先生方のご苦労を否定するわけではないです。自分の父も、産婦人科勤務医を辞めて開業してお産をとっていましたけど、やっぱり一人で妊婦さん見るのはどうしても大変ですから。
分業して、大きな病院ではリスクの大きい分娩を取り扱ったり、何かあった時にすぐに妊婦を受入れれるシステムをもっと整備していただくと。
そして、 開業医の先生のところでは妊婦健診やローリスクの分娩を担当していくというシステム化が大切になってくると思いますね。
いずれにしても、妊婦さんが安心して妊娠期間を過ごして、分娩を迎えられるような環境作りが大切なんですね。まあ、僕個人のレベルでは、お産をされている施設や勤務医の先生方をバックアップできる産婦人科開業医という存在でありたいと思っています。
- ご出産された患者さんに何かプレゼントされているそうですね。
 お母さんにとっても、子どもにとってもお産ってやっぱり人生の記念だと思うので、
何か思い出になるものがあればと思っていました。でも、自院では分娩をとってないので、帰省分娩やセミオープンシステムなどで、妊娠後期まで僕の所で妊婦健診できた方だけですが、4Dエコーも含めて妊娠中の超音波検査写真から作製したBGM 付きのDVDとメッセージカードを分娩後に送っています。
お母さんにとっても、子どもにとってもお産ってやっぱり人生の記念だと思うので、
何か思い出になるものがあればと思っていました。でも、自院では分娩をとってないので、帰省分娩やセミオープンシステムなどで、妊娠後期まで僕の所で妊婦健診できた方だけですが、4Dエコーも含めて妊娠中の超音波検査写真から作製したBGM 付きのDVDとメッセージカードを分娩後に送っています。
妊娠初期早々に他院に紹介した妊婦さんにも分娩結果がわかれば、なるべくカードだけでも送るようにしています。
- 子育てをされた父親として親子の絆づくりの経験談を教えてください。
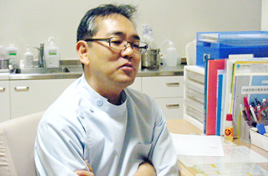 胎教用に色んな音楽のCDを買ってきてやってました。子宮動脈の拍動音が入ったCDとかね(笑)。
胎教用に色んな音楽のCDを買ってきてやってました。子宮動脈の拍動音が入ったCDとかね(笑)。
胎教とかが、どう子どもに影響しているのかは本当のところは分からないけど、色々CDを選んでは買って聴かせてみたり、そうすることでいつの間にか「親」ってことを自分で認識していったと思います。
取材/文章 谷 結実(Eu-D)



